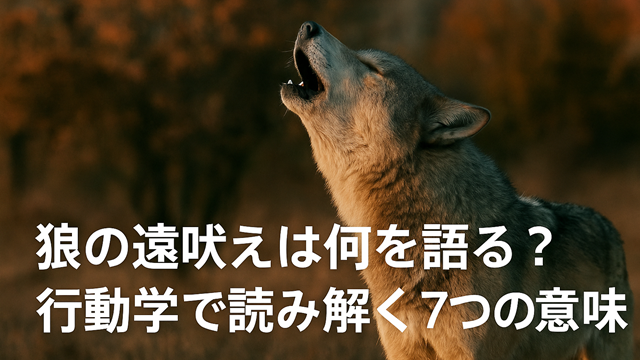夜の静寂を切り裂くように響く「ウォーーン」という狼の遠吠え。
満月の夜にこそ聞こえる、そんなイメージが強いですが、実は遠吠えには「仲間との合図」から「縄張り宣言」「求愛の声」まで、驚くほど多彩な意味が隠されています。
本記事では行動学の視点から、遠吠えの音域や発生タイミングといった基本データを押さえつつ、「群れの再集合」「テリトリー警告」「狩りの合図」など、7つの具体的な役割をわかりやすく解説します。
狼の遠吠え|基本を押さえよう

荒野に響くオオカミの遠吠えは、私たち人間にとっても神秘的で魅力的なサウンドです。
しかし、その「声」はどんな特徴を持ち、どのような状況で多く聞かれるのでしょうか。
まずは遠吠えの音の基本と、季節や時間帯による傾向について押さえておきましょう。
遠吠えの音域・周波数と聞こえる距離
オオカミの遠吠えは低く長く伸ばす独特の音で、これが遠くまで届く秘訣です。
遠吠えの主な周波数(基本周波数)はおよそ150Hzから780Hz程度と低めで、最大で12もの高調波(ハーモニクス)を含むことが知られています。
ピッチ(音の高さ)はほぼ一定か滑らかに変化し、途中で何度か方向を変えることもあります。
この低音域かつ持続的な発声は野山で減衰しにくく、遠距離通信に非常に適しています。
実際、記録によればオオカミの遠吠えは最長で10マイル(約16km)先にまで届いた例があります。
開けたツンドラ地帯であれば16km、森林内でもそれに近い広範囲に響き渡るのです。
このように驚くほど遠くまで届く遠吠えは、広大なテリトリーを持つオオカミにとって欠かせない長距離コミュニケーション手段と言えます。
どのタイミングで遠吠えが多い? 季節・時間帯別データ
では、オオカミはいつ遠吠えすることが多いのでしょうか?季節や一日の中での傾向について、観察研究から読み解いてみます。
長期モニタリングの結果、冬から初春(繁殖期)にかけて遠吠えが増え、夏にかけて減少する明確な季節変化が報告されています。
たとえば米国イエローストーン国立公園での10年に及ぶ観察では、2月の遠吠え頻度は5月の約4倍にも達しました。
2月はちょうど繁殖シーズンのピークであり、この時期にオオカミの血中の生殖ホルモン(テストステロンやエストラジオール)が最高値を示すことと遠吠え頻度の増加は見事に一致しています。
繁殖期以外でも、秋から冬にかけては群れ間のなわばり意識が高まるため遠吠えが活発になり、春から夏にかけて子育てに入ると他群れへの警告的な遠吠えは減る傾向があります。
つまり寒い季節ほど遠吠えは増え、子オオカミの誕生直後には控えめになるという季節パターンがあるのです。
一日の中では、夜間から明け方、夕暮れ時など薄明薄暮の時間帯に遠吠えが聞かれることが多い傾向があります。
オオカミは夜行性・薄明薄暮性の動物であり、自らの活動が活発になる時間帯にあわせて声を交わすからです。
加えて、夜の静かな空気は音が伝わりやすく、遠吠えには理想的な「通信環境」になります。
一方、真昼の暑い時間帯などでは遠吠えは少なめです。
気温が高く日差しが強いとき、オオカミは活動自体を抑え気味にし、長距離の発声も生理的負担が大きくなるため遠吠えも減ると考えられています。
実際、高温時ほど遠吠えは減ることが観察から示唆されています。
このように、涼しく静かな夜ほど「オオカミの合唱」が起こりやすいのです。
行動学で読み解く! 狼の遠吠えが持つ7つの意味
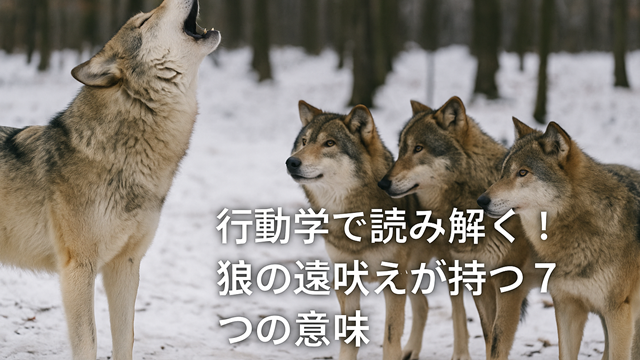
オオカミの遠吠えにはどんな意味や目的があるのでしょうか?
行動学の知見から、代表的な7つの理由に沿って詳しく見ていきましょう。
状況によって使い分けられる遠吠えの役割を理解すれば、あの声が伝えている「メッセージ」が見えてくるかもしれません。
1. 群れの位置確認と再集合
広大なテリトリーを駆け巡るオオカミにとって、仲間の所在を確認し再び集まることは死活的に重要です。
遠吠えはまさにそのためのホーミングビーコン(位置確認信号)の役割を果たします。
オオカミの群れ(パック)は狩りの最中などによく散り散りになりますが、離れ離れになった個体はすぐに遠吠えを開始し、仲間から応答があるまで吠え続けることが知られています。
これは「ここにいるよ!みんなどこだ?」と呼びかけているわけですね。
そして遠く離れた仲間もそれに遠吠えで返答し合うことで、お互いの位置を把握して再集合するのです。
実際、遠吠えの主要な用途の一つはパックの集合合図であり、狩りの前後によく群れ全体で一斉に遠吠えする様子が観察されます。
視界の利かない森の中や広い谷を隔てた場所でも、この長距離通信手段があれば互いを呼び寄せることができます。
遠吠えは群れを物理的に結束させる「接着剤」のようなものだ、と表現する専門家もいます。
2. テリトリー宣言と侵入者への警告
オオカミは明確なテリトリー(縄張り)意識を持つ動物であり、遠吠えは「ここは俺たちの縄張りだ」という音の看板の役割も果たします。
他の群れに対して自分たちの存在を知らせ、境界線を示すためにパック全体で遠吠えを響かせるのです。
実際、遠吠えは他群れへの威嚇や縄張り主張として用いられ、ライバル狼に「近づくな!」と警告する効果があります。
「侵入者よ、我々はここにいるぞ!」という明確なメッセージであり、これ以上近寄ればただでは済まないという警告でもあるのです。
興味深いのは、オオカミが合唱で遠吠えするとき、各個体が少しずつ異なる音程でハモる点です。
同じ音階でユニゾンするのではなく微妙にズラすことで、実際よりも多くの頭数がいるかのような音の錯覚を生み出しているのです。
この声のトリックによって、自分たちの群れを大きく聞かせ、敵対的な他群れに対して数で勝っているように思わせる効果があると考えられます。
遠吠えによる存在アピール&ブラフで無用な接近戦を避ける、オオカミは賢く音を使って縄張りを守っているのです。
3. 狩りの開始・終了シグナル
オオカミの遠吠えは狩りの際のチームワークにも一役買っています。
群れで協力して獲物を追うオオカミは、狩りの前後にも遠吠えを活用します。
典型的には、狩りに出発する直前にパック全体で遠吠えし合う場面がよく観察されます。
まるで出陣前の士気高揚のエール交換のようにも聞こえますが、互いの居場所を確認し「さあ行くぞ!」と気持ちをひとつにする意味合いがあるのでしょう。
また、狩りに成功した後にも遠吠えが響くことがあります。
満腹になったオオカミたちが月夜に揃って歌うように遠吠えする様子は、一種の勝利宣言や祝宴のようにも感じられます。
このビクトリーホール(勝利の遠吠え)は、実利的には離れていた群れの仲間に「獲物が取れたぞ、集合せよ!」と知らせる役割も考えられます。
実際、オオカミは獲物を仕留めて食事を終えた後、現場にいなかった仲間を呼び寄せるために遠吠えすることがあるのです。
狩りの開始から終了まで、遠吠えはパックの協調行動を支える合図として機能していると言えるでしょう。
4. 子狼とのコミュニケーション
オオカミの遠吠えは基本的に遠距離向けの大音量コミュニケーションですが、子オオカミ(パップ)との関係にも関わっています。
ただ、注意したいのは、生まれて間もない子狼たちは耳も十分に聞こえず遠吠えの「言葉」をまだ知りませんし、成長するまで遠吠えをすることもほとんどないという点です。
実際、ごく幼いパップは遠吠えをほとんどせず、代わりにクンクンと鳴いたり甘えた声でコミュニケーションをとります。
遠吠えらしい遠吠えを始めるのはもう少し成長してからで、生後約半年~1年未満のヤングウルフ(イヤーリング)になると、ようやく遠吠えを試みるようになります 。
とはいえ、幼いオオカミの遠吠えは大人とは少し異なり、最後に子犬のような高い鳴き声(キャンキャンというような吠え声)が混じることが観察されています。
声変わり途中の少年が頑張って低音ボイスを出そうとして裏返ってしまうようなイメージでしょうか。
このようにパップ自身が立派に遠吠えできるようになるには時間が必要ですが、親狼や他の大人の狼たちは、パップに対して遠吠え以外のやり方でコミュニケーションを取ります。
近距離では優しく鼻先で鳴いたり甘えるような高い声(クィーンという鳴き声)で子供たちに指示を与えたり安心させたりします。
また巣穴や待機場所(ランデブーサイト)付近では、むやみに大声で吠えて他所の狼に居場所を知らせないようにしているとも考えられます。
繁殖期が終わり子育てシーズンに入ると、群れは他群れとの縄張り争いよりも身内の安全に専念し、派手な遠吠え合戦は控えめになるという報告もあります。
こうしてパップが十分成長するまでは静かに守り抜き、やがて子狼たちも群れの遠吠えコーラスに参加していく、遠吠えは次世代への「教育」と「団結」のツールでもあるのです。
5. 求愛・繁殖期のパートナーコール
冬から初春にかけての繁殖期、オオカミ達の遠吠えにはロマンスの要素も加わります。
繁殖相手を探す、あるいはパートナーとの絆を深める目的で、遠吠えが活発化するのです。
実際、繁殖期直前~最中にはオオカミの遠吠え頻度が明らかに上昇し、配偶者探しのために遠吠えする頻度が高まることが確認されています。
群れを離れて新たな伴侶を求めて旅する「ローンウルフ(一匹狼)」は、広い荒野の中で遠吠えによって自分の存在をアピールし、相手からの応答を期待します。
同種の異性に自分の居場所を知らせるラブコールのようなものです。
また、既にパック内でペアになっているオス・メスのつがい(アルファオスとアルファメス)は、繁殖期に特に仲睦まじく遠吠えのデュエットを披露することがあります。
二頭でハモるように遠吠えし、互いの絆を再確認するとともに、周囲の群れに「私たちはペアだ」と示しているのでしょう。
イエローストーンでの研究でも、繁殖シーズン中の遠吠えの増加はオオカミの血中ホルモン値(発情に関わるテストステロン等)の季節変化と相関することが示されており、遠吠え頻度のピークが繁殖行動に由来する可能性が高いと報告されています。
つまり、オオカミ達がひときわ熱心に遠吠えを交わす冬の夜、その背景には愛を求める声が響いているのかもしれません。
6. 群れ内ランクを示すボイスディスプレイ
オオカミの遠吠えは対外的なコミュニケーションだけでなく、群れ内部の社会的地位(ランク)を映し出す一面もあります。
群れには明確な上下関係があり、通常、遠吠えの合唱をリードするのは最上位のペア(アルファオス・アルファメス)です。
リーダーが遠吠えを開始すると他のメンバーも次々それに呼応する形で吠えますが、その遠吠えの最中や後で群れ内に小競り合いが起こることがあります。
合唱が終わった途端、上位の個体が下位の個体に対してうなり声を上げたり軽く噛み付いたりする場面が観察されるのです。
これは「今の遠吠え、調子に乗り過ぎじゃないか?」とか「ちゃんと序列をわきまえろよ」といった社会的な秩序維持のための行動と考えられています。
実際、「群れで遠吠えすると最後に口論になることがあるが、それは最下位のメンバーを大人しくさせ序列を保つためではないか」と指摘する専門家もいます。
また、興味深い研究結果として、群れの仲間が遠吠えで呼び交わす頻度は、その仲間同士の社会的な結びつきやランクによって左右されることがわかっています。
ある実験では、群れから一頭のオオカミを連れ出して他個体の反応を調べましたが、リーダー格のオオカミがいなくなった場合に残された個体が示す遠吠え頻度は、下位の個体がいなくなった場合に比べて顕著に高かったのです。
さらに、遠吠え量の増加はストレスホルモン(コルチゾール)の上昇とは結び付かず、むしろ「大事な仲間だから心配で呼んでいる」ことが示唆されました 。
これは、遠吠えが単なる感情的発作ではなく、誰がいなくなったか(=その個体の群れ内での重要度)をオオカミたちが認識し、それに応じて柔軟に発声行動を変えていることを意味します。
まとめると、遠吠えは群れ内のボイスアピール&チェックでもあり、その響きには「誰が群れの主役か」「誰が誰を慕っているか」といった社会のヒエラルキーが反映されているのです。
7. ストレス発散や仲間内の絆強化
遠吠えには明確な実利的目的だけでなく、オオカミ同士の感情の共有や絆を深めるという役割もあります。
時には特にこれといった外的理由も無く、オオカミたちが揃って遠吠えを始めることがあります。
こうした「なんとなく合唱」の裏にもちゃんと理由があります。
まず、仲間がいなくて寂しい時のストレス発散・気晴らしとしての遠吠えが挙げられます。
前述の実験で、オオカミは仲の良い仲間がそばにいない時にストレスホルモンのレベル以上に遠吠えを増やす傾向が確認されました。
近しい仲間が離れてしまった不安や寂しさに対し、遠吠えをすることで「早く戻ってきて!」と呼びかけると同時に、自身の不安を紛らわそうとしているのかもしれません。
このように遠吠えは仲間とのコンタクト維持に役立ち、離れていても声を交わすことで安心感を得ているようにも見えます。
また、一斉遠吠えには仲間同士の連帯感を高める効果もあります。
明確な理由がなくとも群れ全体で遠吠えする行動は、オオカミたちにとって一種の「合唱による一体化」の時間なのでしょう。
専門家の中には「社会的遠吠え(ソーシャル・ハウリング)は仲間を見つけたり集めたりするためだけでなく、単に楽しみのため(just for fun)に行われることもある」と指摘する人もいます。
人間で言えばカラオケで一緒に歌うようなもので、特に用事がなくても皆で声を出すこと自体が絆を深めるレクリエーションになっている可能性があります。
実際に「一緒に遠吠えする群れは結束が固い(The pack that howls together stays together)」という言葉もあります。
遠吠えのひとときは、オオカミにとって仲間と感情を共有しストレスを発散する大切な時間なのです。
狼の遠吠えに関するよくある誤解と真実
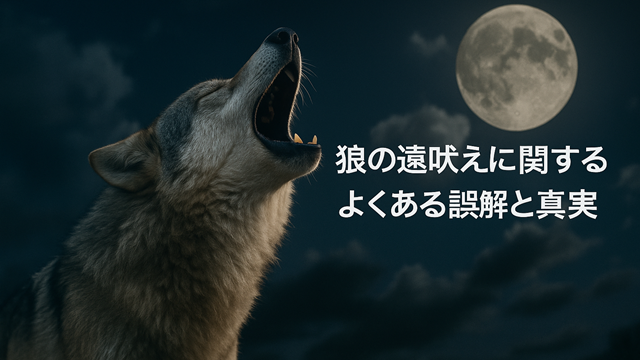
古くから神話や物語で語られてきたオオカミの遠吠えには、いくつかの誤解も付きまとっています。
ここでは狼の遠吠えに関する代表的な誤解を取り上げ、最新の知見にもとづいて真実を明らかにします。
「満月の夜に遠吠え」は本当か? 統計と研究結果
オオカミ=満月というイメージはあまりに有名です。
映画やイラストでも、満月に向かって狼が吠えるシーンが定番になっています。
しかし「オオカミは満月の夜に特に遠吠えする」という説に科学的根拠はありません。
研究者たちは月の満ち欠けと狼の遠吠え頻度との関連性を調べましたが、満月だからといって遠吠えが増えるという証拠は見つからなかったのです。
実際、オオカミの遠吠えは新月であろうと半月であろうと起こりますし、月相による顕著な増減は観察されていません。
ではなぜ満月と遠吠えが結び付いたイメージが広まったのでしょうか?
一つには、オオカミが遠吠えする夜間という時間帯と、夜空でひときわ目立つ満月という視覚的インパクトが結び付いたためでしょう。
オオカミは前述の通り夜によく遠吠えしますが、それは活動時間や音の伝わりやすさによるものであって、月そのものに吠えているわけではないのです。
遠吠えの際に狼が顔を上に向けるのも音を遠くに飛ばすための姿勢であり、決して月に向かって叫んでいるわけではありません。
米国の国立公園局も「月の満ち欠けは狼の発声行動に何の影響も及ぼさない。そして人気の伝承に反して、狼たちは月に向かって遠吠えしているわけではない」とはっきり言及しています。
満月の晩に遠吠えが聞こえると神秘的に感じられますが、それは偶然夜空に月が輝いているだけで、狼にとって月は関係ないのだと覚えておきましょう。
人間への威嚇サインではない? 襲撃との関連性
遠吠えの響く夜、森の中で狼の声を聞くと「こちらを威嚇しているのでは?」「襲われる前兆では?」と不安になるかもしれません。
しかし、狼の遠吠えは人間に向けられたメッセージではありません。
基本的にオオカミは人間を獲物とは見なしておらず、遠吠えはあくまで他のオオカミへの通信手段です。
実際、オオカミは人間と遭遇した際、多くの場合攻撃するどころか逃げ去ることが知られています。
人間に対しては非常に用心深く、むやみに近づこうとはしません。
歴史的に見ても、オオカミが人を襲う事例は非常に稀で、現代においては北米でオオカミに襲われて死亡した記録は極めて例外的と言われます(過去に報告された襲撃例も、その多くは狂犬病に罹患した個体や、人間側が幼子を無防備に野に放った中世ヨーロッパでの事例など特殊な状況に限られます。
つまり、森で遠吠えが聞こえても「狼がこちらを狙っている」わけではありません。
むしろ彼らは自分たちの仲間同士で会話しているのであって、こちらとしては「ああ、どこかで狼たちがコミュニケーションしているな」と捉えるくらいが適切です。
もし万一オオカミが人間に対して警戒や威嚇を示す場合は、遠くから遠吠えするのではなく、もっと直接的な唸り声や短い吠え声(バーク)で警告するでしょう。
それも人間が不用意に巣穴や子供に近づいた時など、防衛本能から出る行動であり、基本的には狼は人間を避ける生き物だというのが真実です。
遠吠え=人間への挑戦状、というホラー映画的なイメージは誤解なのです。
遠吠えと吠え声(Bark)の違い
オオカミの発する声には「遠吠え(howl)」以外にも様々なバリエーションがありますが、その中でもイヌ科特有の「吠え声(ほえごえ、英: bark)」との違いは興味深い点です。
日本語ではどちらも「吠える」と表現されることがありますが、動物行動学的にはhowl(遠吠え)とbark(短い吠え)は区別されます。
簡単に言えば、遠吠えは上述してきたように長く尾を引く遠距離通信用の声であり、吠え声(bark)は短く鋭い近距離警告音です。
オオカミも犬のように「ワンワン」と吠えることがありますが、その頻度はイエイヌよりずっと少なく控えめです。
狼がバーク(bark)を発するのは主に驚いた時や警戒・威嚇が必要な場面です。
例えば不意に何かに驚かされたオオカミは「ウッ、ウッ」と低めの短い吠え声を2〜3回発し、その後その場から後退します。
連続して何十回もキャンキャン吠え続ける犬とは対照的に、狼の吠えはせいぜい数回で終わるのが普通です。
また母狼は巣穴に危険を感じた時、子狼に伏せるよう促すために低い唸り声混じりの吠え声(バーク・ハウル)を出すこともあります。
いずれにせよ吠え声は目の前の危険や敵に対する「これ以上近づくな!」という警告として用いられます。
一方、遠吠えはここまで見てきたように仲間との長距離コミュニケーションや縄張り宣言などに用いられるため、目的も性質も異なります。
つまり、吠え声(bark)は近場の危機に対処するシグナル、遠吠え(howl)は遠くの仲間に呼びかけるシグナルと考えると分かりやすいでしょう。
狼の遠吠えに関するQ&A

最後に、オオカミの遠吠えに関して読者が抱きがちな疑問をQ&A形式で補足します。
狼は単独でも遠吠えする?
はい、群れから離れた一匹狼(ローンウルフ)も遠吠えします。
遠吠えは群れ内の通信だけでなく、孤立した個体が仲間や配偶者を探すための手段にもなります。
実際、単独行動中の狼が夜空に向かって遠吠えを上げ、見知らぬ遠方の狼からの応答を期待する、まさに「おーい、誰かいないか?」と呼びかけているような状況が観察されます。
また、自分の存在を周囲に知らせてテリトリーを主張する目的で、一匹狼が遠吠えする場合もあります。
もっとも、孤独な狼にとって遠吠えは諸刃の剣でもあります。
大勢の群れと違い一頭きりの狼が自分の居場所を明かすことは、他の群れにとっては格好の攻撃対象になりかねません。
そのため、単独の狼は他群れのテリトリー内では遠吠えを控えるという行動も報告されています。
実際、ある保護区では「単独行動中の狼が遠吠えすると、競合する群れに襲撃される危険があるため慎重になる」と指摘されています。
つまり一匹狼も遠吠えはしますが、場所と状況を選んで用心深く行うのです。
群れを呼ぶための心細げな声も、場合によっては静かに胸にしまっておく——野生で生き抜く知恵と言えるでしょう。
人工環境下(動物園)でも遠吠えする理由は?
はい、飼育下のオオカミも遠吠えします。
たとえ動物園や保護センターといった人工環境にいても、遠吠えはオオカミにとって本能的な行動だからです。
広大な縄張りを必要としない状況でも、仲間とのコミュニケーションや習性による発露として遠吠えは見られます。
動物園のオオカミたちは、夜間になると野生同様によく遠吠えすることがあります。
これは夜行性のリズムに従っているからでもあり、また周囲が静かになる夜にこそ遠吠え本来の「呼び合いたい」という衝動が高まるのかもしれません。
さらに人工環境では、人間社会の音(遠くのサイレンや他の動物の鳴き声)に反応して遠吠えすることもあります。
これも彼らにはサイレンの音が仲間の遠吠えのように聞こえ、本能的に「ハウリング合戦に参加しなくては!」となるからでしょう。
以上のように、環境が人工的でもオオカミのアイデンティティは失われません。
狩りをしなくてもお腹が減らなくても、仲間と声を交わし合いたい、生来の習性がある限り、オオカミは遠吠えを続けるのです。
遠吠えの長さに意味はある?
遠吠えの長さ(持続時間)自体に明確な「意味」があるわけではありませんが、状況によって長短が使い分けられる傾向はあります。
一回の遠吠えは平均して数秒から長くて10秒前後持続しますが、必要に応じて何度も繰り返されることがあります。
重要なのは、遠吠えが文節のある言語のような決まった長さの信号ではなく、その時々のモチベーションによって長くなったり短くなったりするという点です。
応答が得られなければ間をおいて再度遠吠えし、何度も繰り返すことで結果的に長時間にわたって吠え続けることもあります。
一方で、獲物を追いかけている最中など興奮状態にあるときの狼は、長々と遠吠えする余裕はなく、代わりに短い吠えや高いピッチの短い遠吠えを発する傾向があります。
実際、研究者の観察では「群れに獲物の仕留め場所を知らせるときには長く滑らかな遠吠えを使い、追跡中は2音節で震えるような高い遠吠えになり、獲物に追いつく直前には短い吠え声と遠吠えの混合音に変化する」と報告されています。
このように文脈によって遠吠えの音調や長さが変化するのです。
したがって、「遠吠えが長ければ○○のサイン」という決まった訳ではないものの、長くゆったりした遠吠えが続くときは狼が落ち着いて何かを呼びかけている(もしくは群れでじっくり合唱している)状態であり、逆に遠吠えが断片的で短いときは狼が興奮・緊張している状態だと推測できます。
いずれにせよ、長さそのものよりも「その遠吠えが置かれている状況」こそが意味を読み解く上で重要だと言えるでしょう。
まとめ~狼の遠吠えの意味と役割がすっきり解消~
狼の遠吠えは単なる「夜の風物詩」ではなく、行動学的に見ると実に多様なコミュニケーション手段でした。
音域や季節・時間帯のデータから、遠距離で仲間を呼ぶ位置確認、縄張りを示す威嚇、狩りの開始・終了シグナル、子狼への声かけ、繁殖期のパートナーコール、ランク維持のディスプレイ、そしてストレス発散や絆強化まで、7つの役割が明らかになっています。
また「満月=遠吠え」や「人への威嚇」という誤解も、最新研究ですっきり解消できましたね。
次に野山で狼の声を耳にしたら、ただ幻想に浸るだけでなく「今この遠吠えは何を伝えようとしているのか?」を想像してみてください。
彼らの声には、群れと生存を繋ぐ深い物語が詰まっています。
参考文献・研究論文リスト
- Encyclopædia Britannica:「Why Do Wolves Howl?(なぜ狼は遠吠えするのか)」オオカミの遠吠えの目的や届く距離、社会的要因について分かりやすく解説 (Why Do Wolves Howl? | Britannica) (Why Do Wolves Howl? | Britannica)。
- Yellowstone National Park, Wolf Project (2016):“Why Wolves Howl” – イエローストーン公園の約10年にわたる観察データ。季節変化や群れ間/群れ内の遠吠え傾向について詳細なレポート (YS 24-1 Why Wolves Howl – Yellowstone National Park (U.S. National Park Service)) (YS 24-1 Why Wolves Howl – Yellowstone National Park (U.S. National Park Service))。
- Range, F. et al. (2013) Current Biology:“Wolf Howling Is Mediated by Relationship Quality Rather Than Underlying Emotional State.”(一部はScienceDaily記事「Wolves howl because they care」に要約) – オオカミの遠吠えがストレスよりも社会的絆に影響されることを示した実験研究 (Wolves howl because they care: Social relationship can explain variation in vocal production | ScienceDaily)。
- IFLScience (2023):「Why Do Wolves Howl At The Moon – Or Do They?」ホリー・ラージ – 満月と遠吠えの神話を科学的に検証し、遠吠えの実際の目的(繁殖期の増加や音の到達距離など)を紹介 (Why Do We Believe Wolves Howl At The Moon? | IFLScience) (Why Do We Believe Wolves Howl At The Moon? | IFLScience)。
- Wolf Sanctuary of PA (2013):「Wolf Communication – Part 1: Vocalization」 – ペンシルベニア狼保護区による記事。遠吠えの物理的特徴(低音・長持続で10マイル届く)や用途(群れの再集合、狩り、侵入者警告、社会秩序)について具体例を挙げて説明 (Wolf Communication – Part 1: Vocalization – Wolf Sanctuary of PA) (Wolf Communication – Part 1: Vocalization – Wolf Sanctuary of PA)。
- International Wolf Center:「How do wolves communicate?」 – オオカミのコミュニケーション(ボディランゲージや臭い・声)に関する解説ページ。遠吠えや吠え声の使い分けについても記載 (How do wolves communicate? | International Wolf Center) (How do wolves communicate? | International Wolf Center)。
- WolfFacts.org:「Do Wolves Attack Humans?」 – オオカミによる人間襲撃の頻度や状況をまとめた記事。歴史的経緯や現代での稀さ、人間に対する狼の基本的な態度についてデータを提示 (Do Wolves Attack Humans? Reasons Why a Wolf Might Attack People) (Do Wolves Attack Humans? Reasons Why a Wolf Might Attack People)。
- Wikipedia英語版:「Wolf communication – Auditory (Howling)」 – オオカミの聴覚コミュニケーションの概要。遠吠えの周波数帯や月との無関係さ、単独狼の遠吠え回避、遠吠えと他の発声(吠え・唸り)の比較など (Howling – Wikipedia) (Wolf communication – Wikipedia)。